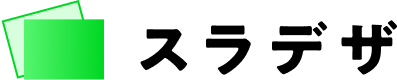参考にしたい時系列・沿革のスライドのデザイン厳選6選!
記事公開日:2024年01月18日
記事更新日:2025年02月25日

インターネット上に公開されている資料の中から、時系列・沿革のデザインが優れているスライドを6つ独自に選びました。
この記事の中から、あなたが作ろうとしているテイストにあったデザインを選んで参考にすれば、
わかりやすくオシャレなスライドを作れること間違いなしです!
「もっと時系列・沿革のスライドを見たい!」と言う方は、沿革のスライドデザイン一覧もご覧ください。
\ もっと見たい方はこちら /
目次
SmartHR社

こちらのSmartHR社のスライドでは、タイムラインを表すチャートと文字のみのシンプルなデザインです。単に時系列の流れを表すためにはタイムラインチャートを使うと効果的です。年が経つごとにグラフが濃くなっている点もポイント。視線の流れをわかりやすくなります。
西暦は縦書きに配置する工夫がされていますね。これにより、シンプルながらもおしゃれな印象を受けます。
また、グラフの背景だけ水色になっているのもポイントの一つ。白背景だと退屈な印象になったり、逆にスライド全体を水色にするとしつこい印象になってしまいますが、一部だけ色を変えることでちょうど良いバランスのスライドを作ることができます。
- タイムラインチャートと徐々に濃くなる配色で、視線の流れを助けてあげましょう
- それでも退屈な印象の場合は、補助的なテキスト(西暦など)を縦書きにしてみましょう。
- それでも退屈な場合は、背景色を一部だけ変えてみましょう。
Overflow社

モノトーンの配色でシンプルなデザインに仕上げられていますが、アイコンを使うことで親しみやすい印象を持てますね。
よく見るとパソコンのアイコンにOffersのロゴが配置されており、細かな部分まで工夫されていることがわかります。
またグラフは右肩上がりになっており、動きのあるデザインになっています。
- モノトーンでシンプルな印象を作れます。
- シンプルすぎて退屈な印象になったらアイコンを使ってみましょう
- 右肩あがりのグラフを使って、動きのあるデザインにしてみましょう

サービスの情報をまとめた一つ目のスライドと比べると、このスライドは会社自体の情報が多いですね。
この資料は「採用ピッチ資料」という求職者に向けた情報資料なので、会社の雰囲気が伝わるスライドを用意しているのでしょう。
徐々に人が増え綺麗なオフィスになってきています。会社の軌跡が伝わる情報構成になっていますね。
スタートアップで働くの醍醐味は急速な会社の成長でしょう。オフィス写真の変遷とともに紹介するのはとてもいいアイデアですね。
また、写真は情報量が多く、配置がけっこうむずかしいデザイン要素です。不必要に配置すると全体的にごちゃごちゃした印象になってしまします。
このスライドでは、白背景と薄いドロップシャドウを使うことで認識しやすいひとまとまりの情報(チャンク)として配置されており、10枚の写真を使いながらもすっきりとした印象を持つことができますね。
- オフィス写真を使って視覚的な変化・成長を伝えましょう。
- 写真をたくさん使うときは、それぞれを独立した情報と伝わるようにしましょう。
- スタートアップに勤めているなら、写真をたくさん撮っておきましょう(後で見返した時に、ノスタルジーを感じることにも役立ちます)
雨風太陽社

ポケットマルシェを運営する、雨風太陽社のIR資料の沿革のスライドデザインです。
IR資料は情報の正確さと網羅性を求められます。どうしてもごちゃっとした印象になってしまうのですが、このスライドは限られた紙面の中でうまくデザインされています。
一つひとつの情報が白の背景とドロップシャドウで囲われています。これには二つのメリットがあります。
ひとつ目は情報を囲うことで、情報量が多くても視線をどこに移せば良いかわかりやすく読みにくさは感じませんね。
ふたつ目。ドロップシャドウを使うことで、後ろに線が通過しているということがわかりやすくなります。
つまり、各情報がいつの話なのかを数直線まで伸びる線に辿りやすくなっています。
- 情報量が多いときは、一つひとつの情報をまとめてみましょう。
- 情報と線が被ってしまうときは、ドロップシャドウを使って通過していることを表現しましょう。
- IR資料じゃない場合は、スライドを分けることも検討しましょう。
Ubie

こちらのUbie社のスライドは沿革を縦に並べたデザインになっています。そして右半分に大胆に写真を使っています。
16:9の横長のスライドではどうしても横に伸びるデザインが多くなってしまいます。しかし、半分に分けることで縦のデザインを作れることになり、スライド全体のデザインで変化をつけることができます。
また、右半分の写真では、彩度(鮮やかさ)と明度(明るさ)を落としています。こうすることで、ノスタルジックな印象を持てます。創業当時の懐かしい思い出を、読む人に追体験できるような効果を感じれます。
- 横に伸びるデザインが多いなら、半分に分割してみましょう
- まだ設立して間もなかったり、沿革に載せる情報が少ない場合も縦書きはおすすめです。
- 写真で与えたい印象によって彩度と明度を調整してみましょう
STORES社

今回紹介した沿革のスライドの中でも特に息を飲むデザインだったのが、このSTORES社のスライド。複数のプロダクトや会社の配置のデザインは苦戦しますが、このスライドでは左に並べることでわかりやすい配置としています。
情報的には経営統合した日の下に配置することも考えられますが、両サイドに余白ができてしまいます。この配置は無意味な余白を避けるために左に揃えてしまうことで解決しています。
各会社のボーダーの色にも注目です。統合前の各社は薄いグレーのボーダーに囲われており、各社を統合したSTORES社のボーダー色は濃いグレーを使っています。こうすることで「結局いまどうなっているのか」を色で表しています。
- 複数のプロダクト・サービス・会社を沿革のスライドに書くときは、上下左右を広く使いましょう
- 無意味な余白が生まれるときは、思い切って左に揃えてしまいましょう
- 結局いまどうなっているのかを表したいときは、他よりも濃い色で囲ってみましょう。
まとめ
今回は、「時系列・沿革」の高品質なスライドを6つ紹介しました。まだもう少し別のデザインを見たい!と言う方は、 沿革のスライドデザインもみてくださいね。
スライドデザインでは、国内の高品質なスライドをまとめたギャラリーサイトです。高品質なスライドデザインを参考にしたい!と言う方は、ぜひご活用ください。
\ もっと見たい方はこちら /